アメリカへの留学
広大な国土と多様性・選択肢の広さが魅力
中学生・高校生の留学の受け入れ先としては、イギリスと並んで最も歴史のある国と言えるのが、アメリカです。私立のボーディングスクールは、全国に約350校存在し、それぞれの学校が特色を持っています。公立校への留学は、学生ビザの発給が1年のみのため、1年間しか在学することができません。
アメリカ留学のメリット・留意点
メリット
- 約350校のボーディングスクールから、自分に合った学校を探せる選択肢の広さ
- 成績優秀者には、奨学金や飛び級、大学への単位持ち越しなど、目に見える形の結果が得られる
留意点
- 気候や時差、英語のアクセントや人種の比率などの地域差による影響を考慮する
教育制度
特長
小学校6年間、中学校2年間、高校4年間(州によって異なります)と、少し日本と似ています。ESL(英語を母国語としない第1外言語としての英語)と呼ばれる留学生のための英語クラスを設置しているところが数多くありますので、英語力が十分でない学生も入学できます。
ほとんどの寮制学校の場合、ガーディアン(現地保証人)は不要ですが、西海岸などの一部では必要な学校もありますので、確認が必要です。
学校生活では、学習だけでなくスポーツや寮ごとの活動、コミュニティー活動などへの参加が奨励されていて、リーダーシップをはじめとするさまざまな能力を発揮する機会が設けられています。
以下に代表的なアメリカの教育制度をご紹介します(州によって異なります)。
- 小学校6年間、中学校2年間、高校4年間
- 小学校4年間、中学校5年間、高校3年間
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary School | Middle School | Upper School | 4-year college | |||||||||||||
| Elementary School | Junior Bording School | Upper School | 2-year college | |||||||||||||
学期
新学期は8月下旬~9月上旬に始まり、2学期、3学期、4学期制です(学校により異なります)。
2学期制の場合、前期は12月中旬頃まで(11月中旬~下旬に感謝祭休暇があります)、後期は1月上旬~5月末、又は6月上旬(途中、3月~4月に2週間ほどの春休みがあります)で1学年が終了します。
入学時の注意点
ビザ取得
学生ビザは、申請者のほぼ全員がアメリカ大使館(または領事館)に出向き、面接を受けます。
エディクムからのアドバイス
9月(または8月下旬)に始まる新学期に備え、6月~7月に始まるサマースクール、または4月開始の語学研修に参加することをお勧めします。
ボーディングスクール(私立寮制学校)費用例
| 学校名 | Cushing Academy | Mercersburg Academy | St. Croix Lutheran High School |
|---|---|---|---|
| 授業料・寮・食費 | $72,850 | $72,925 | $37,600 |
| ESL費 | $7,500 | - | - |
| 合計 | $80,350 | $72,925 | $37,600 |
| 1USD=150円(2023年10月現在) | ¥12,052,500 | ¥10,938,750 | ¥5,640,000 |
上記は1学年間の授業料・寮・食費の基本費用です。その他に航空券代、医療保険代、入学金、雑費(教科書、テクノロジー、アクティビティ費用など)預け金、小遣い、ビザ申請費、エディクムのサポート費用などが別途かかります。
アメリカへの留学体験談
エディクムの子どもたちは、ボーディングスクール、サマースクール、公立校含め、さまざまな学校に留学していきました。以下に紹介していますので、ご覧ください。

















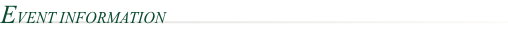 知る・触れる・イベント情報
知る・触れる・イベント情報


カンボジアでのサービスプロジェクトに参加して
私は、現在コロラド州にあるFountainValley School に通っています。 高校生活が残すところ1 年となった夏休み。大学進学への準備だけではなく有意義な時間を過ごしたいと思い、民間団体主催の高校生ボランティアプログラムに参加しました。多数の選択肢がある中、友人がいることで親近感があるカンボジアで、子供たちに英語を教えるプログラムを選択しました。
空港に着いた途端、湿度と温度の高さに驚き、これからこの過酷な気候の中活動するのが少し不安になりましたが、現地のコーディネーターの方が親近感の持てる女性で、日本のことを色々と質問してくれたりしながら、私達の不安な気持ちを解きほぐしてくれました。初日のWelcome Dinner ではタランチュラやコオロギの料理が出てきました。コーディネーターの人に、“これはカルシウムだからもっと食べた方が良い”と推されましたが、足だけ食べるだけで精一杯でした。
このプログラムに参加する以前、カンボジアは、発展途上国で治安もあまり良くない国という印象でした。実際のカンボジアは、都市のプノンペン近くはイオンやスタバなどもある近代都市でしたが、車で20 分も走れば未舗装の道路となり、裸足で歩く子供の姿を多く見かけ、また住居はほとんどが、高床式住居で、家畜を住居スペースの下に飼っている家が多く驚きました。学校へは河を渡らなければいけませんが、橋が整備されていないため、毎日船に乗らなければなりませんでした。このような環境の中でも、生徒たちはとてもフレンドリーで明るく、積極的に質問して来ました。クメール語と英語でのコミュニケーションは、とても難しかったですが、大繩飛びや折り紙を一緒にしているうちに次第にコミュニケーションが取れるようになり、数名の生徒が自分の名前を呼んでくれ た時はとても嬉しかったです。
平日は毎日午前中英語を教え、午後は壁塗り活動をするのが私たちの主なボランティアワークでした。1 年生から6 年生まで1 学年1 クラス編成で、しかも、ひとクラスの人数も数十人なので、学年を超えて皆仲良く遊んでいました。クラスの中で英語力が異なる生徒達に、限られた時間の中で、どうやったら生徒達が退屈せず、効率良く英語を学べるかを他のグループのメンバーとも何度も話し合いを重ねました。お互いの言語がわからない中教えるのはとても難しかったですが、最終日には生徒達は皆に手紙を書いてくれて、飴やスノードーム、折り紙をプレゼントしてくれました。午後は色褪せていた校舎を真新しい綺麗なペイントを使って塗り直すという途方もない作業でしたが、授業が終わった子供達がお手伝いしてくれたお陰で、2 週間後には校舎全体が新築同様になりました。
子供全員が学校に行けるのが当たり前の日本ですが、カンボジアではそうではなく、アンコールワットなどの有名な観光地ではお土産を観光客に必死に売っている子を何人も見ました。また、学校には電気は通ってないので、クーラーはありません。いくら屋根があるといっても、外は毎日38 度の世界で、教室にあるのは2 台の扇風機だけ。一つ20 ドルの扇風機が購入できない過酷な環境下でもみんな文句ひとつ言わず授業を受けていました。
小学校では多くの生徒が日本からの寄付と思われるくまモンなどのキャラクター物の洋服、公文式のカバン、日本製の自転車などを使っていました。今回発展途上国の貧しさを初めて自分の目で見、また、実際に子供達が他国からの寄付の品物を使っている場面に何度も遭遇し、寄付の大切さを実感しました。
今回参加した私たちのグループだけではこの状況を解決するには微力すぎるかもしれませんが、寄付をアメリカの学校でお願いすればもっと多くの人が支援してくれると思い、夏休み後学校で募金活動をしました。自分にできることはほんのわずかなことですが、こうした発展途上国の状況を多くの人に伝え、小さな活動を続けて行くことが、発展途上国を支えて行く力になると強く感じ、今後も機会があれば、支援活動を続けて行こうと思いました。