高校生の留学とは?
エディクムがサポートする高校生の90%は、留学先の高校を卒業することを目的とした留学です。多くの学生は、日本の高校を辞めて留学し、高校卒業後には大半の学生が国内外の専門学校や大学へ進学をしています。
その他に、希望や目的に応じ数ヶ月〜1年間ほどの短期留学を希望する学生もいますが、日本の学校を休学して1年間留学でも、画一的な交換留学(学校選びができない。終了後は帰国しなければならない)ではないので、それぞれの目的に合わせて世界中から本人に合った学校を選ぶことができます。留学先が気に入り、1年間留学から高校卒業目的に留学プランを変更する学生もいます。
近年、海外の高校は身近な進学先の一つとなりました。卒業後は海外の大学だけでなく、日本の大学にも帰国子女枠・アドミッション入試などができるようになってきました。高校卒業後の語学留学や大学留学よりも、自分で考え行動できる「自立」した大人へのステップとなることが多いです。
高校生の留学の特長
語学力
初めて留学する高校生の英語力は「ゼロ」レベルから英語検定準1級レベルまでさまざまです。そのため、留学後に一般の授業についていけるだけの英語習得にかかる時間は、学生によって異なります。初級ESL(英語を母国語としない又は第1外国語としての英語)プログラムのある学校には英語力が心もとなくても入学できますが、ESLのない(または、上級レベルしかない)学校では、英語の試験、高校入学前に現地の語学学校で数ヶ月~1年程度の英語を学ぶことなどを要求されることがあります。
エディクムからのアドバイス
日本では「英語ができる人」=「英語を話すのがうまい人」と認識している人が多いと思います。しかし、本当に「英語ができる人」というのは、文法が身についていて、文章力があり、読解力が高い人です。もちろん会話が上手であれば生活は便利ですが、留学先で最も必要とされるのは、「読解力」と「筆記力」です。日本での英語学習は文法に力を入れている学校が多いですが、正しい英語を話す、書くためには、避けて通れないものです。特に高校から留学を考えている方は、英語の文章がどのようにして成り立っているのかを理解することが重要です。
留学時期
中学3年生から
高校留学とはいえ、エディクムには中学3年生から留学する学生が多くいます。海外には高校が4年制(中学3年生~高校3年生)の学校が多く、中学3年生へ入学すれば高い英語力が要求されない学校もあります。また、ほとんど留年することなく4年間で卒業し、英語力がネイティブのレベルに達する学生もいます。この時期の留学は、国内のインターナショナルスクールに通っていた学生も目立ちます。
高校1年生から
中学校を卒業することで日本式義務教育システムから解放されるため、家族からの留学許可が出やすくなります。ESL(英語を母国語としない又は第1外国語としての英語)初級プログラムを受けなければならない英語力の低い学生でも、学校によっては3年間で卒業できます。可能であれば、中学生の時にサマースクールを体験することをお勧めします。
高校2年生から
将来のことを自ら真剣に考えだすのが高校2年生。
- 「世の中の仕組みが少しわかり夢が世界に広がった」
- 「大学受験を考えると今が1年間留学できる最後のチャンスだ」
- 「受験の失敗で進学した高校に不満がある」
など、留学のきっかけはさまざまです。留学生受入校のほとんどでは日本での単位を認めているので、高校1年生を修了していれば理論的には高校2年生から入学できます。しかし、授業についていけるだけの英語力がない学生は、学年を落として高校1年生から3年間を考えるようにお勧めしています。この期間の1年間、勉強の時間を余分に費やすことは、これからの人生にプラスであってもマイナスにはならないでしょう。
高校3年生から
高校2年生の留学ケースと同様、日本で高校2年間をきちんとした成績で修了していれば、留学先で高校3年生になる資格ができます。しかし、相応の英語力がなければ留学して1年間での卒業はほぼ無理だと考えられます。英語習得に1年程度をかけ、合計2年間の留学で卒業できると考えましょう。なお、ボーディングスクールや私立校では高3(12年生)からの受け入れをしない学校もあります。
留学例
エディクムのOB・OG 7,800人以上の中から、高校生から留学したケースをご紹介いたします。
ケース1
| 16歳 | 高校1年生 |
|---|---|
| アメリカ サマースクール 参加 |
|
| 16歳 | 高校1年生 |
| アメリカ ボーディングスクール 入学 |
|
| 18歳 | 高校卒業 |
| アメリカ ボーディングスクール 卒業 |
|
| 18歳 | 大学1年生 |
| アメリカ 4年制大学 入学 |
|
| 20歳 | 日本の大学に編入 |
| 日本 4年制大学の3年生に編入 |
|
| 22歳 | 大学卒業 |
| 日本 大学を卒業 |
|
 |
|
| 24歳現在 | 大手ホテルに就職 |
| 日本 大手ホテルに就職 |
|
ケース2
| 16歳 | 高校1年生 |
|---|---|
| ニュージーランド ボーディングスクール 入学 |
|
| 18歳 | 高校卒業 |
| ニュージーランド ボーディングスクール 卒業 |
|
| 18歳 | 大学1年生 |
| オーストラリア Griffith大学 入学 |
|
| 22歳 | 大学卒業 |
| アメリカ 半年間、アメリカの大学で研修 |
|
 |
|
| 22歳現在 | デンマーク資本の会社に就職 |
| 日本 デンマーク国籍の会社の日本法人に就職 |
|
ケース3
| 16歳 | 高校1年生 |
|---|---|
| スイス ボーディングスクール 入学 |
|
| 18歳 | 高校卒業 |
| スイス ボーディングスクール 卒業 |
|
| 18歳 | 大学1年生 |
| アメリカ 4年制大学 入学 |
|
| 22歳 | 大学卒業 |
| アメリカ 大学を卒業 |
|
 |
|
| 23歳現在 | アメリカで就職 |
| アメリカ アメリカの日系通信企業に就職 |
|
※上記の年齢・学年は、日本で使用される年齢・教育制度による学年としております。
高校生の留学実績・体験談
エディクムの子供たちは、ボーディングスクール、サマースクール、公立校含め、さまざまな学校に留学していきました。以下に紹介していますので、ご覧ください。





















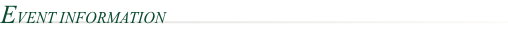 知る・触れる・イベント情報
知る・触れる・イベント情報


留学がきっかけで起業、社長へ
K.O.くんは、日本の中学校を卒業後、Bethlehem College(タウランガ・ニュージーランド)のYear10(中学校3年生に相当)へ入学し、3年半後に同校を卒業しました。
【K.O.くんのプロフィール】 1991年12月、富山県小杉町(現射水市)で生まれ、小学校3年生まで富山県、小学校4年生から6年生は長野県松本市、そして中学校3年間は新潟県妙高市で過ごす。その後、高校時代にカナダへ行った兄、オーストラリアに10年住んでいた叔母の影響で、その他にもいくつかの理由から(後述する)、ニュージーランドへの留学を決める。 Bethlehem College卒業後は、早稲田大学政治経済学部経済学科へ入学し、大学1年時に、翻訳・通訳のウェブサービス会社を起業、その後、売却、そしてその資金を元手に、大学2年時に民泊事業を開始する。2015年、大学4年時に法人化。現在、ホテル・ブライダル・不動産・人材事業を中心に9社、30事業の会長を務める。
まさかの受験失敗から、ニュージーランドへ
最初に、留学できる環境を提供してくれた、両親には感謝をしてもしきれない。今でもよく考えることがある。もし私が、留学していなかったらどうなっていただろうと。 私の家系は、父をはじめ親族の大多数が医師であり、当然私も、将来的は医師になると幼少期から思っていたし、おそらく留学をしていなければ、昔から想像していたルートを歩み、今頃医師になっていただろうと、ふと考えることがある。そんな私が、なぜ留学をすることになったか。前述で、兄や叔母の影響が、と述べたが、最大の理由は、高校受験に失敗したからである。当時の私は、中学校に昼頃に登校し、ランチを食べ、友人達と遊んで、友人達の部活を遊び歩いた後、学校の部活外で習っていた極真空手に行く、という、自分でいうのもなんだが、適当な日々を送っていた。一方で、当時、新潟県内の中学校で最も生徒数の多い中学校で、試験の前日には徹夜で寝不足になりながら教科書を熟読し、隠れてこっそり勉強はしていたことから、自慢ではないが、定期試験では常に上位の成績を取得していた。そういった成績結果だけはしっかり出しているということもあり、学校に出席しなくとも煩く言われることもなく、かなり厄介な中学生であったと今にして思う。当然、その様な行動や、短期記憶に頼りきって毎度の試験に臨んでいたこともあり、高校受験も2週間前から勉強を始め、県内一の進学校のみを受験した結果、見事、不合格となったのである。中学の卒業式前の2月であったが、当時は根拠のない自信家だったこともあり、当然滑り止め校も受けておらず、高校で浪人することも想定しておらず、不合格の結果通知を受け取るという(今だから笑えるが)不測の事態に直面し、放心状態となってしまった。 その様ななか、3歳上の兄を短期の高校留学に送り出していた両親が、折角の機会なので、むしろこの結果を前向きに捉え、海外の高校へ進学したらどうか、と勧めてくれた。これから英語ができることが当たり前の世の中になり、また、幼い頃から日本以外の国も見てきて色々な文化、考え方を知り、視野を広げた方が良いと言ってくれた両親には、本当に感謝している。そして、当時やんちゃだった私は、何をしでかすか自他ともに分からず、自然豊かでのびのびと安全に暮らせる国、ニュージーランドへと留学することとなった。
中学校3年をもう一度やり直す
英語はもちろん学年でトップクラスの成績を誇っていた私ではあったが、あくまで試験上の話で、それまで英語を話したことは殆どなかった。最後に海外へ行ったのは、中学2年生の時に2週間、叔母のいるメルボルンだったが、いざ現地に到着しても全く英語を聞き取れず、ひたすら黙り続けていた私である。そんな英語が話せない私は、まずYear10として、ニュージーランドの経済の中心地オークランドから南東に300km程度に位置するBay Of Plentyのタウランガという街にある、Bethlehem Collegeへ入学した。当時は、中3をやり直すのか!一刻も早く高校に進学したい!という焦った気持ちがありつつも、留学準備に2ヶ月かけ、入学した時は、既に6月であったこともあり、2月に学期が始まり11月に終わる南半球の学校のため、最初の半年は、英語の勉強と割り切り、勉強をすることとした。
2回のホームステイ暮らし
滞在方法はホームステイであった。最初の家庭は、過去10年近くにわたり留学生を受け入れているベテランホストファミリーであった。3人の子供がいたが、既に3人とも成人しておりオーストラリアで就職していたため、私は、ホストファザーとホストマザー、台湾人留学生の3名の家族の一員として加わった。ホストマザーが看護師で、ホストファザーが家事を中心に行っており、ニュージーランドらしい家庭で過ごせたのは、大変貴重な経験となった。ニュージーランドでは、つい先日まで国のトップである首相が女性であったし、就業におけるジェンダーギャップが世界的に見てもほぼ無いニュージーランドでは、今や、大学入学者は男性より女性の方が多いという現状もある。また、別の家庭も見てみたいという気持ちもあった私は、最後の年Year13の1年間は、既に香港人、韓国人の2名の留学生を受け入れていた、評判も良かったトンガ人のホストファミリー宅で過ごした。
打ち込んでいたスポーツ
ニュージーランドといえば、ハカやオールブラックスで有名な、国民的スポーツ、ラグビーである。私も高校は、中学から続けていた空手の延長で、地元のキックボクシング、ブラジリアン柔術、総合格闘技ジムに通いつつ、ラグビーに打ち込んだ。ラグビーは1軍には体重80kg以上ないと入れないという規定があり、身長171cmしか無い私は、肉とポテトを毎日食べ、体を大きくし、重めの服を着こんで、ギリギリ体重制限をパスすることができた。私の学校、Bethlehem Collegeは男女共学であったが、よく試合をしていた男子校は現地のマオリというニュージーランドの先住民族が多く、また、ハカを必ずといっていいほど試合前に踊り、地響きが鳴り、試合前には毎回ビビっていた。練習は週6とほとんど毎日あったが、練習という感覚もなく、皆遊びの延長でやっている感じであり、非常に楽しい思い出の一つとなった。週末の試合後には、ハンギというマオリ伝統料理を楽しみながら音楽を流し、パーティーに明け暮れ、楽しんだ。スポーツや音楽は、文化や風習の壁を越え、仲良くなるだけでなく、精神面も鍛えられ、コミュニケーションの上達にもつながり、一石三鳥であり、是非、これから留学する方にも、留学中の方でもまだ取り組んでいない方がいれば、現地の学生と是非、何かしら一緒に活動することをお奨めする。将来の財産に繋がるのは間違いない。
留学して良かったこと、総評
将来のためになるからと、留学に送り出してくれた両親に感謝すると共に、準備から、何も知らない土地での不安だらけの学校生活、留学後の進路相談まで徹底的にサポートして頂いた、エディクムのスタッフの方々には改めて深く感謝申し上げたい。
留学して身についたことは大きく3つある。 まず1つ目に、勿論、「英語力」である。今日、日本の大学在学中に留学する人は多いが、早い程、吸収力が違う。ただ、早すぎても良いという事ではなく、日本の文化、言葉遣い、経験を一通り吸収した中学卒業後というタイミングも、非常に良かったと振り返っている。 2つ目に、「柔軟な考え方」である。現地の人間だけでなく、自分と同じようなインターナショナルな留学生達とも交流を深めることにより、文化の壁を越え、物事をまずは受け入れ、吸収し、考えられる力が身についた。 そして最後に、「度胸」である。経験がない領域や場所での展開を0からワクワクして取り組めるようになった。これは今の仕事で、どの様な領域の事業でも私が展開できることに繋がっている。 最後に、現在、留学中の学生も、留学をこれから考えている学生も、この良い経験を最大限に活用すべく、是非色々と留学中にトライして欲しいと思う。